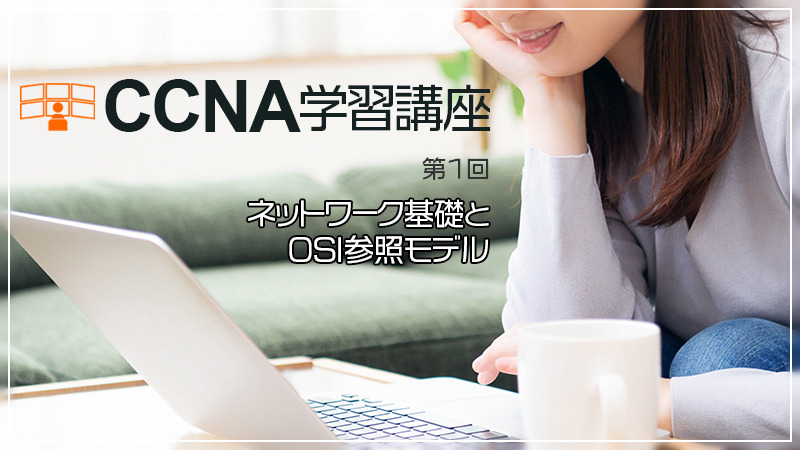第1章 ネットワーク基礎とOSI参照モデル
ネットワークとは
今回出てくる用語
1. ネットワークとは
2. コンピューター・ネットワークとは
3. スタンドアローンとは

ちゃん
みなさんこんにちは!
これから「ネットワーク」に関してご説明していきます。
では早速、なるほどくんに質問です。
「ネットワーク」って何ですか?

くん
ネットワーク・・・
友達とLINEをしたりインターネットで検索したりすることですか?

では、「物流ネットワーク」と言う場合の「ネットワーク」は、今なるほどくんが説明したネットワークと同じですか?

それもネットワークと言う同じ言葉ですね。。。
ダメで、降参です。。。。

ネットワークという言葉を使ったものは他にも、たくさんありますよね。
交通ネットワークや人間の血管とか神経などもネットワークと呼ばれていますよね。
では、これらの共通点は何でしょうか?

ネットワークって何か蜘蛛の巣みたいというのは以前聞いたことがあるのですが、蜘蛛の巣みたいな感じで何かと何かをつなげるみたいな意味でしょうか?

惜しいです!
でも、勘所は良いですよ。
正解は「網」と「運ぶ」というキーワードが関連しています。

なるほど!
確かに、交通網とか物流網とかいいますからね。

つまりネットワークとは、
網状に繋がっていて。
何かを運ぶ、そのことを示す言葉なのです。
例えば、コンピュータで考えてみると、
コンピュータ同士がケーブルで網状につながっていて、情報(データ)を運ぶ。
※この場合、「コンピュータ・ネットワーク」と呼ばれます。

なるほど!確かに最近では、
「ネットワーク」=「コンピュータ・ネットワーク」と考えてる人も多いけど、ネットワークという意味は別にあったのですね。

そうです!
なので、これから私が説明するのはコンピュータ・ネットワークのことだということを覚えておいてください。
コンピュータが誕生した頃、コンピュータは単体で他のコンピュータと接続しない形態で利用していました。この利用形態をスタンドアローンと言います。
コンピュータが進化するにつれて、コンピュータを相互に接続し利用されるようになります。
複数台のコンピュータをケーブルや電波などで相互に接続して、相互に情報を
やりとりする仕組みをコンピュータネットワークと言います。
この仕組みは単にネットワークとも言います。
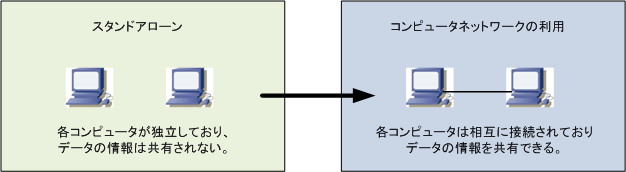
まとめ
1. ネットワークとは
→ 網状に繋がっていて。何かを運ぶ、そのことを示す言葉
2. コンピューター・ネットワークとは
→ 複数台のコンピュータをケーブルや電波などで相互に接続して、相互に情報をやりとりする仕組み
3. スタンドアローンとは
→ コンピュータ単体で他のコンピュータと接続しない形態
コンピュータネットワークの分類
今回出てくる用語
- スニーカーネット
- LAN
- WAN
- インターネット
- イントラネット

ここまでで、ネットワークについて理解いただけたと思います。
では、次はコンピュータネットワークの分類に関してです。
これを説明するには、初期のネットワークまで遡っていく必要があります。

初期のネットワークですか?

はい!
初期のネットワークは「スニーカーネット」と呼ばれるもので、
言葉の起源は、スニーカーを履いた人がデータを持ち運ぶというところからきています。

持ち運ぶということは、昔あったフロッピーディスクなどで運ぶということですか?

そうです!
コンピュータ同士をケーブルで繋ぎデータをやり取りさせることがなかった以前は、スニーカーを履いた人が情報の入ったフローピーを持ち運んでいたことから、スニーカーネットと呼ばれています。

なるほど!面白いですね。

はい!でも、これは非常に無駄の多い作業(リソースの無駄使い)でした。

確かに、プリンタで印刷をする時にもフロッピーディスクを持ち歩いたりしないといけないのは面倒ですね。プリンタの争奪戦も起こりそう。。

そうです!
そこで、この無駄を解決するためにLANというものが作られました。
スニーカーネットから、現在主流のLANに進歩したのです。
LANとは現代のネットワークの、基盤となるシステムです。

なるほど。
では、LANを使うとどのように無駄が解決されるんでしょうか?

一言で言うと、リソースが重複するのを防ぐことで無駄を解決することに成功しました。
LANの中にいる皆でリソースを共有し合うと言い換えることもできます。

なるほど!
1台のプリンタをみんなで使えるようにしたり、1つのデータをみんなが使うようにしたりして
リソースを共有し合うことができるようになったと言うことですね!

はい!なるほどくん良いですね!
では、そうなると今度はもっと広い範囲でリソースの共有をしたくなってきます。
こちらのビルのLANとこちらのビルのLANを結ぼうと言うイメージですね。

確かに、私の家からなるはやちゃんの家とで写真共有などもしたいですからね。

そうですね。そう言う時にLANとLANを結んでの広い範囲でのネットワークを、WANと呼びます。
スニーカーネットから、LANへ、そしてWANへ、と進化を遂げていったのです。
コンピュータネットワークは規模に応じて下記3つに分類することができます。
- LAN
- WAN
- インターネット
1. LANとは
Local Area Network(ローカルエリアネットワーク)の略で、同じ建物の中にあるコンピュータ、プリンタ、サーバなどを接続してデータをやり取りするネットワークのことです。
LANといっても、家庭内で数台のPCを相互接続しているLAN(家庭内LAN)や、企業内で数百台のPCなどを相互接続しているLAN(企業内LAN)などがあります。
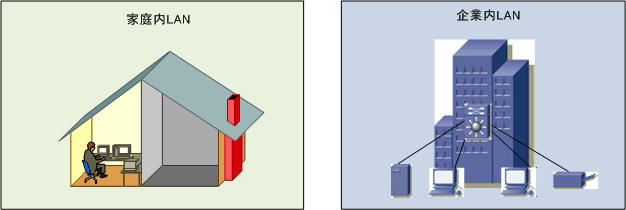
2. WANとは
Wide Area Network(ワイドエリアネットワーク)の略で、地理的に離れた場所にあるコンピュータなど相互接続して、データをやり取りするネットワークのことです。
WANはNTT、KDDI、ソフトバンクといった通信事業者が提供するサービス(広域イーサネット、IP-VPNなど)を利用しています。
このWANによって、本社と支店の企業内LANを相互接続したり、異なる場所にある大学のキャンパスLANを相互接続したりすることが可能となります。
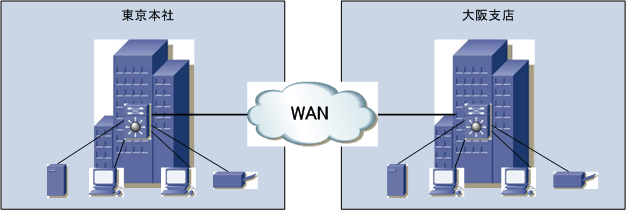
3. インターネットとは
世界の全てのネットワークを相互接続した巨大なコンピュータネットワークのことです。
家庭内LAN、大学キャンパスLAN、企業内LANなど、世界中の様々なネットワークが接続されています。
インターネットは全体を統括するコンピュータは存在せず、全世界に分散された無数のコンピュータが少しずつサービスを提供することで成り立っています。例えば、なるはやプログラミングのWebサイトもインターネットの一部です。
インターネットには、PCだけではなく、スマホなどの様々なデバイスからアクセスできます。
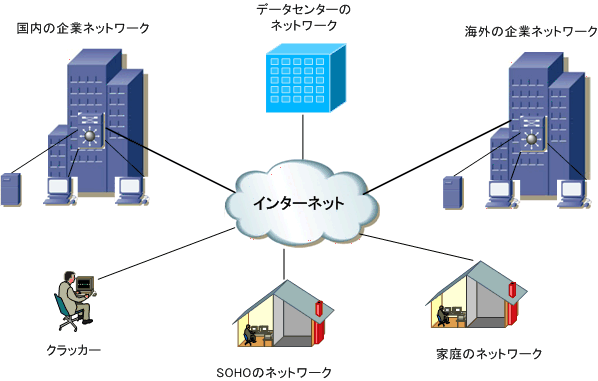
おまけ:イントラネットとは
イントラ(内部的な)ネットでは特定の組織内メンバーだけが閲覧できるネットサービスがあったり、特定の組織内のメンバーだけでメールの送受信ができるなど閉じたネットワークのことです。
※ インターネットが世界規模の開かれたネットワークであるのに対し、イントラネットは企業規模の組織内ネットワークです。
まとめ
1. スニーカーネットとは
→ スニーカーを履いた人が情報の入ったフローピーを持ち運んでデータをやり取りしていたから生まれた言葉
2. LANとは
→ Local Area Network(ローカルエリアネットワーク)の略で、同じ建物の中にあるコンピュータ、プリンタ、サーバなどを接続してデータをやり取りするネットワークのこと
3. WANとは
→ Wide Area Network(ワイドエリアネットワーク)の略で、地理的に離れた場所にあるコンピュータなど相互接続して、データをやり取りするネットワークのこと
4. ネットワークとは
→ 世界の全てのネットワークを相互接続した巨大なコンピュータネットワークのことです。
5. イントラネットとは
→ 企業規模の組織内ネットワークのこと。
ネットワークストレージとは
今回でてくる用語
1. ストレージ
2. DAS
3. NAS
4. SAN

ここまでで、ネットワークを使ってデータをやり取りするということは理解できましたね?

はい!ネットワークってすごいなと改めて思いました!

いいですね!
では、次にデータというものはどこかにしまっておく必要がありますよね?

確かに、データをしまっておく場所って必要ですよね。

はい!そこで、次はそのデータをしまっておく箱(装置)「ストレージ」についてご説明しますね。
ストレージとは
ストレージとは、デジタル情報を記憶/保存する装置のことで、ハードディスク、MO、CD-R、磁気テープなどが該当します。皆さんも使ったりみたことはあると思います。
また、ストレージには接続形態で分類されており、大きく3種類があります。
1. DAS
2. NAS
3. SAN
DAS ( Direct Attached Storage )
この用語のポイントを簡単に!
・データをしまっておく箱だよ
・コンピュータに直接くっつけるよ
・NASと対比するための用語だよ
DASは、コンピュータに直接くっつけた外付けハードディスクのことです。
DASは主に、NAS(この次に説明します)と対比させるために使います。
ネットワークに挿すNASに対し、コンピュータに挿すDASとの位置付けです。
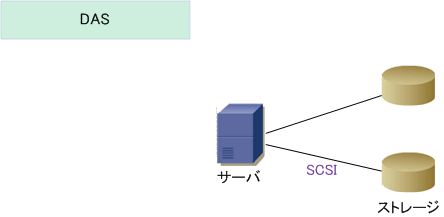
NAS ( Network Attached Storage )
この用語のポイントを簡単に!
・データをしまっておく箱だよ
・ネットワークを経由して使えるよ
NASは、ネットワークを経由して使える外付けハードディスクのことです。
普通の外付けハードディスクは、パソコンにブスっと挿して使いますよね?
ブスッと挿されたパソコンは、挿した外付けハードディスクを自分のハードディスクとして使うことができます。これがDASでしたね。
それに対してNASは、ネットワークにブスッと挿して使います。
ブスッと挿されたネットワークの中にいるパソコンは、挿した外付けハードディスクを自分のハードディスクとして使うことができます。
ただし、みんなが自分のハードディスクとして使えるので、結果としてデータを共有してる状態になります。
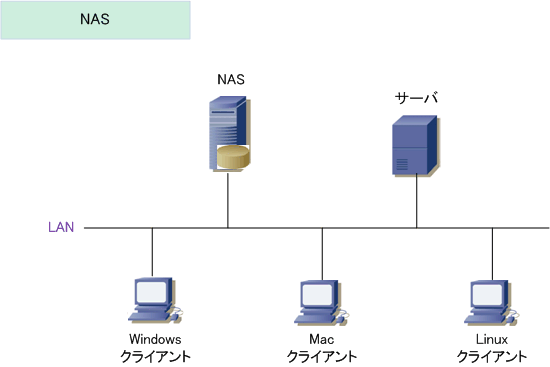
SAN ( Storage Area Network )
この用語のポイントを簡単に!
・NASとやり取りするための専用ネットワークだよ
・ネットワークそのものを指す場合もあれば、やり方を指す場合もあるよ
NASは、ネットワークにブスッと挿して使うというのは前の章でお伝えしましたが、ブスッと挿されたネットワークの中にいるパソコン達は、挿した外付けハードディスクを自分のハードディスクとして使うことができます。
しかし、NASには弱点があります。
それは、みんなが同じネットワークを使っているので、画像を保存する人やメールを送信する人などみんなが思い思いに作業をすると、データが届くのが遅くなったりしてしまうのです。
そこで、そんな問題を解消するために、NAS(というか外付けハードディスク)は、独立することにしました。
具体的には、外付けハードディスクたちで独自のネットワークを作り、パソコンとやり取りすることにしたのです。
もちろん、このネットワークは自分たち専用です。
インターネットのデータやメールのデータはやってきません。
これで、外付けハードディスクたちは、他の影響を受けないので高速でやり取りができます。インターネットやメールのデータからしても、余計な奴らがいないので助かるでしょう。
これが、「外付けハードディスク専用のネットワーク」が「ストレージエリアネットワーク」DASです。
ストレージとは、データをしまっておく箱でしたね。
エリアとは、「地域」、今回は「区域」と訳しましょう。
ネットワークはそのままですね。
そしてこれらを繋げて考えてみると、文字通り「データをしまっておく箱(storage)用の区域(area)なネットワーク(network)」がSANです。
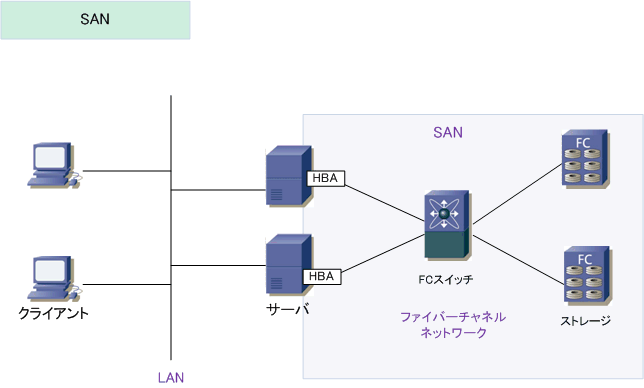
まとめ
1. ストレージとは
→ データをしまっておく箱(装置)のことで、デジタル情報を記憶/保存する装置のことで、ハードディスク、MO、CD-R、磁気テープなどが該当
2. DASとは
Direct Attached Storageの略で、簡単に訳すと
「直接(Direct)取り付けた(Attached)データをしまっておく箱(Storage)」という意味で、コンピュータに直接くっつけた外付けHDD(ハードディスク)のことです。
3. NASとは
Network Attached Storageの略で、簡単に訳すと
「ネットワーク(Network)に取り付けた(Attached)データをしまっておく箱(Storage)」という意味で、ネットワークを経由して使える外付けHDD(ハードディスク)のことです。
4. SANとは
Storage Area Networkの略で、「データをしまっておく箱(storage)用の区域(area)なネットワーク(network)」のことです。
※NAS や SAN の接続形態によって利用するストレージのことを「ネットワークストレージ」といいます。
ネットワークトポロジーとは
今回出てくる用語
1. ネットワークトポロジー
2. スター型ネットワーク
3. ハブ型ネットワーク
4. リング型ネットワーク
5. 物理トポロジー
6. 論理トポロジー
ネットワークトポロジーとは
この用語のポイントを簡単に!
・ネットワークの形だよ
・接続形態を点と線でモデル化したものだよ
ネットワークトポロジーとは
ネットワークの”分類“(トポロジー(topology))という意味です。
簡単に言うと、
「ネットワークの形」をカッコつけて難しく言った用語と捉えてください。
言い換えると、ネットワークの接続形態を点と線でモデル化したものです。
では、具体的にみていきましょう。
ネットワークというのは、線のつなぎ方やデータの流れ方によっていくつかの形態に分類することができます。以下が代表的なものです。
1. スター型ネットワーク
2. バス型ネットワーク
3. リング型ネットワーク
スター型ネットワーク
その名の通り、見た目が星っぽいから付けられた名前です。
スター型ネットワークは、親機を置いて、すべての通信をその親機経由で行うネットワーク形態を「スター型ネットワーク」と言います。
現在の主流のネットワーク形態です。
1本のケーブルに障害が発生した場合でも他の機器との通信に影響は出ませんが、
集線装置に障害が発生すると全ての機器との通信に影響が発生します。
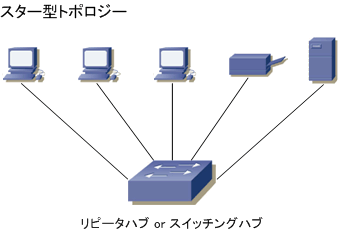
バス型ネットワーク
ケーブルを1本用意して、そのケーブルにそれぞれのコンピュータをつなぐネットワーク形態を「バス型ネットワーク」と言います。
中心となるケーブルが「バス」という名前だからこの名前が付けれられてます。
大昔に使用されていたネットワーク形態です。
1本のケーブル障害が発生すると全ての機器と通信ができなくなるデメリットもあります。
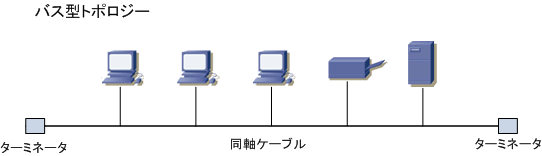
リング型ネットワーク
輪っかにしたケーブルを1本用意して、その輪っかケーブルにそれぞれのコンピュータをつなぐネットワーク形態のことを「リング型ネットワーク」と呼びます。
見た目が輪っかだからリングと呼ばれています。
こちらも、過去に利用していたネットワーク形態です。
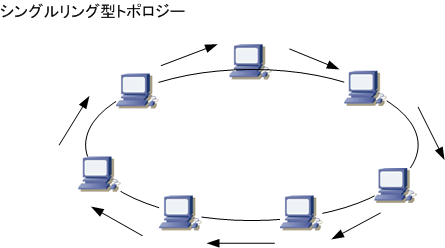
以上、今回例に出した「スター型ネットワーク」「バス型ネットワーク」「リング型ネットワーク」はネットワークのモデル(模型)のことです。
実際にネットワークを作るときは、線の数が増えたり、つなぐコンピュータの数が減ったりします。ネットワークそれぞれによって、形は違うはずです。
ですが、細かい違いを無視して一般化したら、この○○型ネットワークのどれかにはなりそうですね。
このように、細かい違いを無視してネットワークの形を抽象化・一般化したものが「ネットワークトポロジー」です。
ネットワークトポロジーには「物理トポロジー」と「論理トポロジー」があります。
「線はどうつなぐの?」に注目して見たのが物理トポロジーです。
「データはどう流れるの?」に注目して見たのは論理トポロジーです。
例えば 、会社で新しく作ったネットワークは線のつなぎ方が星っぽい形でした。
ですが、中を流れるデータはバケツリレー方式、輪っかの中を進むように受け渡しされる形だったのです。
このようなネットワークは「物理トポロジーはスター型で論理トポロジーはリング型だね」と言ったりします。
トポロジー(topology)とは”分類”という意味です。
つまり、
物理トポロジーというのは、機械やケーブルの繋げ方(物理的に)から見たネットワーク形態の分類です。
論理トポロジーというのは、データの流れ(論議的に)から見たネットワーク形態の分類です。
ということも一緒に覚えておきましょう
まとめ
1. ネットワークトポロジーとは
→ネットワークの形をモデル化(抽象化・一般化)したもの
2. スター型ネットワークとは
→親機を置いて、すべての通信をその親機経由で行うネットワーク形態
3. バス型ネットワークとは
→ケーブルを1本用意して、そのケーブルにそれぞれのコンピュータをつなぐネットワーク形態
4. リング型ネットワークとは
→輪っかにしたケーブルを1本用意して、その輪っかケーブルにそれぞれのコンピュータをつなぐネットワーク形態
5. 物理トポロジーとは
→機械やケーブルの繋げ方(物理的に)から見たネットワーク形態の分類
6. 論理トポロジーとは
→データの流れ(論議的に)から見たネットワーク形態の分類
プロトコルとは
今回出てくる用語
1. プロトコル
2. プロトコルスタック
3. TCP/IP
4. プロトコルの標準化を推進する機関

次は、コンピュータや機器同士でどのように通信を行っているのかを見ていきましょう。

はい!

では、まず質問です。
なるほど君は、日本人と話をする時、何語で会話をしますか?

もちろん、日本語で会話をしますよ!

そうですね。
今、なるほど君は相手が日本人なら、日本語で話すという暗黙の了解が頭の中にあり、そう答えましたね?

そうです!
日本人だから日本語で会話をするのは当たり前ですよね!?

はい。その通りです。
会話には、暗示的にせよ、明示的にせよ、「日本語で話す」というように、約束事が必要となります。

なるほど。

そして、このどうやって会話をするか
つまり、どうやって通信を行うかのルールがコンピュータや機器の間でも約束(ルール)が決まっています。

なるほど!
次はその通信のルールの説明ということですね!?

その通り!
では、説明していきますね!
プロトコルとは
この用語のポイントを簡単に!
1. 簡易な用語に変換するとこんな感じ
→ コンピュータや機器が通信する上でのお約束事だよ
2.身近な例で考えよう
→ 会話をするときと同じで、お互いが日本語で話すというルールがあるから会話が成立する。もし、会話のルールがなく、一方が日本語、一方がアラビア語だったら全く会話は通じないのと同じこと。
プロトコル(protocol)とは、条約とか取り決めと言う意味です。
なので、ネットワークの世界でプロトコルという時は、主に通信(の)プロトコル(お約束)という意味合いで使われます。
簡単に言うと、「通信する時のお約束事」をカッコつけて言ったのが「プロトコル」です。
これには、主に下記2つのルールが決められています。
・コンピュータ間でどのようにデータを送るのか
・どれだけのデータを送るのか
コンピュータ間をただLANケーブルなどで物理的に接続しただけでは、相互に通信することができませんがこのプロトコル(具体的にはIPやTCP等)を使用することで、コンピュータとコンピュータが通信できます。
プロトコルスタックとは
この用語のポイントを簡単に!
・ 通信プロトコルの詰め合わせのこと
・ その通信をするのに必要なお約束事を全部まとめたものだよ
コンピュータ間の通信において使用されるプロトコルは1つではなく、役割の異なる複数のプロトコルを使用しています。
例えば、現在見ているWebサイトを閲覧するためには、IP、TCP、HTTPなどのプロトコルを使用しています。
Webブラウザを使用してWebサイトの画面を見るためにHTTPが使用されていますが、その下の階層ではTCP、さらにその下の階層ではIPが使用されています。
このように、通信に必要な複数のプロトコルを、階層構造で構成するプロトコル群のことをプロトコルスタックと言います。
また、プロトコルには数多くの種類があります。
現在最も主流な通信プロトコルといえばTCP/IPです。
TCP/IPはLAN、WAN、インターネットなどで最も使用されているプロトコルです。
TCP/IPといっても、通信する際にTCPとIPだけを使用する訳ではありません。
その他にUDP、FTP、Telnetなどの数多くのプロトコルを使用しますが、それらを総称してTCP/IPと呼んでいます。
| 通信プロトコルの体系 | 使用されるプロトコルの例 | 主な用途 |
| TCP/IP | IP, ICMP, TCP, UDP, SMTP, HTTP…. | 全てのネットワーク |
| IPX/SPX | IPX, SPX, NCP…. | Netware OS環境のLAN |
| AppleTalk | AARP, DDP, RTMP, AEP….. | Mac OS環境のLAN |
TCP/IPとは
この用語のポイントを簡単に!
・通信プロトコルだよ
・インターネットで使われているよ
・セットで書かれているが、「TCP」と「IP」と分かれているよ
TCP/IPとは、通信するときに使うお約束事(通信プロトコル)のひとつのことです。具体的に説明すると、
安全性重視で通信するときに使うお約束事「TCP」とインターネット用のお約束事「IP」を一緒くたにした表現です。
TCPは、「Transmission Control Protocol(トランスミッション・コントロール・プロトコル)」の略で、送ったデータが相手に届いたか、その都度確認しながら通信するやり方です。
例えば、相手の言ったこと復唱しながら会話をするイメージです。
ちゃんと届いたか確認しながらやり取りをするので
1.漏れなく伝わる可能性が高い
2.スピードが遅くなる
といった特徴があります。一方、
IPは、「Internet Protocol(インターネット・プロトコル)」の頭文字を取って
その名の通り
「インターネット」用の「プロトコル(お約束事)」
です。
TCP / IPの「/」は「アンド(and)」の意味です。
コンピュータがインターネット回線に接続する際には必ず、このIP(インターネット用のお約束事)が登場します。
しかし、IPだけでは安全に通信ができないためTCPに助けを求めるのです。
そのため、TCP / IPとひとまとまりで覚えておくと良いでしょう。
ここまでで、コンピューターや機器が通信するためには同じ体系の通信プロトコルを使用する必要があることが理解できたと思います。
例えば、下図においてコンピュータAがTCP/IP対応の通信プロトコルを使用しているならコンピュータBもTCP/IPプロトコルを使用していないとプロトコルが異なる(約束ごとが異なる)ので相互に通信できません。
※例えば、人と人がコミュニケーションする際に、日本人同士なら日本語を使用しないと会話が成立しない事と同様のことです。
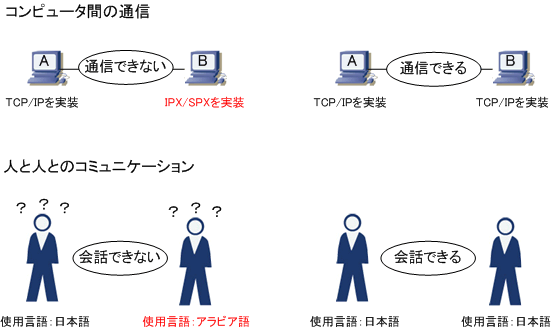
プロトコルの標準化を推進する機関
この用語のポイントを簡単に!
・国際的な基準を決めている団体だよ
・団体の名前と説明を覚えちゃおう
従来はプロトコルを策定する主体は、ネットワーク機器製品を製造するハードウェアのメーカーでした。
しかし、ネットワークシステムが普及すると異なるメーカー機器同士の接続が重要になりました。
そこで、プロトコルを国際機関で管理して標準化する流れが強まりました。
国際的に標準化されたプロトコルを採用しているネットワーク機器である場合、他社メーカーの通信機器であっても相互にネットワーク通信をすることが可能です。
現在、プロトコルの標準化を推進する機関に以下のような機関があります。
| 標準化の機関 | 正式名称 | 説明 |
| ISO | International Organization for Standardization | 国際標準化機構、国際規格の策定が目的。 |
| ITU | International Telecommunication Union | 国際電気通信連合。無線通信と電気通信の標準化。 |
| IETF | The Internet Engineering Task Force | インターネット技術の標準を策定。RFCを発行。 |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | 世界規模の電気工学・電子工学の学会。 |
| ANSI | American National Standards Institute | 米国国家規格協会。米国内の工業分野の標準化組織。 |
まとめ
1. プロトコルとは
→コンピュータや機器が通信する上でのお約束事
2. プロトコルスタックとは
→通信プロトコルの詰め合わせ
3. TCP/IPとは
→通信プロトコルのことで、安全性重視で通信するときに使うお約束事「TCP」とインターネット用のお約束事「IP」を一緒くたにした表現
4. プロトコルの標準化を推進する機関とは
→プロトコルの国際的な基準を決めている団体
OSI 参照モデルとは – 1
今回出てくる用語
・OSI参照モデル
・OSI参照モデルの7つの階層
・データのカプセル化

ここまでで、コンピュータや機器が通信をするときのルールがあることがお分かり頂けたと思います。
では、次はそのルールに関してもっと詳しくみていきましょう!

はい!お願いします!
OSI参照モデルとは
この用語のポイントを簡単に!
・通信機能の共通ルールのことだよ
・国際標準化機構(ISO)ってところが作ったよ
・ネットワークエンジニアならマスターしないといけないポイントだよ
OSI(Open Systems Interconnection)参照モデルとは、国際標準化機構(ISO)が作ったデータ通信機能におけるモデル(イメージ図)のことです。
簡単にいうと
「ISOという団体が、通信機能の仕組みをふんわりと定義したもの」と捉えてください。
OSI参照モデルは、ネットワークを勉強すれば必ず出てくるものですが、分かったような分からないような気分になる単語ですので、何回もこの章を読み返してもらうことをオススメします!
それでは、詳しく見ていきましょう。
まず通信をするときには、送り手と受け手で同じルールを共有する必要があることは、もうお分かり頂けましたね?
片方が日本語で話しかけたのに、もう一方が英語でお返事をしたのでは、コミュニケーションが成り立ちませんよね。
それと同じです。
ところが、以前はメーカーごとに好き勝手なルールを作って、好き勝手に通信をしていました。
例えると、あるメーカーさんが作った機器は日本語でやり取りしていましたが、別のメーカーさんが作った機器は英語でやり取りしていたり、また別のメーカーではアラビア語でやり取りをしていたりとカオスな状態になっていました。。
これでは、別のメーカーさんが作った機器とやり取りしようとしても言葉が通じません。
「他のメーカーの製品とは通信できない」残念な状況だったのです。
NECのパソコンとPanasonicのパソコンで通信ができないというような残念な状況だったのです。
これは不便ですよね?
そんな状況を見た、頭の良い人達が「共通ルールを作ってしまえば、メーカーが違っても通信できるんじゃないか?」と考えました。
そこで、国際標準化機構(ISO)という団体さんが「データ通信機能は、こんな感じにしてね!」なルール(モデル)を作りました。
これで、このルールを満たしている製品は、異なるメーカーでも通信ができるようになりました。
そして、この異なるメーカーの製品でも通信できるようにするために作られたルール(モデル)が「OSI参照モデル」です。

ちょっと、ここでコーヒーブレークしましょう!

はーい!
コーヒーブレーク:OSI参照モデルの歴史

OSI参照モデルは、1984年に策定されたルールです。

そうなんですね!

今では、OSI参照モデルはネットワーク通信の基本的な考え方として、ネットワークエンジニアのお仕事の中でも会話で話しが出てきますので、ぜひ覚えてくださいね!

はい!復習しておきます!

では、続いてOSI参照モデルを使って、どうやって通信が処理されいてるのかをご説明していきます。
OSI参照モデルの階層構造
この用語のポイントを簡単に!
・OSI参照モデルで、どうやって通信が処理されているかの話しだよ
・7つの層(レイヤ)に分かれているよ
・通信全体の問題を簡単に、修正しやすくするために階層(レイヤ)を分けているよ

ここは、難しいのでぜひ何度も復習をしてね。

では説明していきます!

まず、どうやって通信は行われるのかを、別の例で考えてみましょう。
では、なるほど君は恋人はいますか?

な、何ですか!?急に!?
い、一応いますよ。
(2次元の〇〇ちゃんだけどね。。。)

では、その子に手紙を出すことを想像してみてください。

て、手紙ですか?

はい!

手紙を相手に送る時にはいくつかの手順がありますよね?

手順ですか?
例えば、内容を考えるとか、封筒を用意するとかですか?

そうです!
手紙を出すためには、主に以下の段階に分かれます。
・内容(伝えたいことを考える)
・表現(手紙に書く)
・伝送物(便箋、封筒、宛名などの記載)
・伝送(郵便屋さん)

なるほど。

そして、これらの段階にはそれぞれ別のルールがあります。

そうですね。
手紙の書き方と、配達の仕方が同じルールなわけないですもんね!

はい!段階に応じて、それぞれルールが必要ですね。
これらをまとめると以下の表になります。
| 段階 | 行うこと・するもの | ルール |
|---|---|---|
| 内容 | 伝えたい事を考える | 明瞭に・簡潔に。 |
| 表現 | 手紙に書く | 相手がわかる言葉で。文語文にする。 |
| 伝送物 | 便箋・封筒・宛名 | 定型の便箋・封筒。切手や宛名の書き方 |
| 伝送 | 郵便局員・郵便トラック | 宛先までの道を決定する |

そして、通信をする時にもこの手紙のような段階やルールが分かれていて、通信が行われるのです。

なるほど!
以下がOSI参照モデルで定義されている、段階です。
7つの階層(レイヤ)と呼びます。
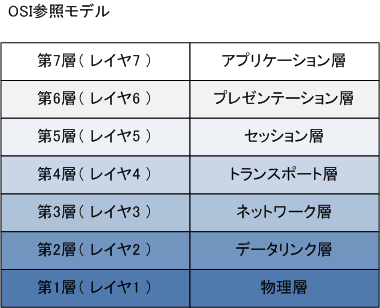 |

上の表でアプリケーション層などを覚える時に、よく使われる覚え方が、それぞれの頭文字を取って、
「ア、プ、セ、ト、ネ、デ、ブ」
と覚えたりします!ぜひ、皆さんも呪文のように唱えてください。
OSI参照モデルの各層では、コンピュータで以下のような役割を担います。詳細は後ほど紹介します。ざっくりで良いので目を通しておきましょう。
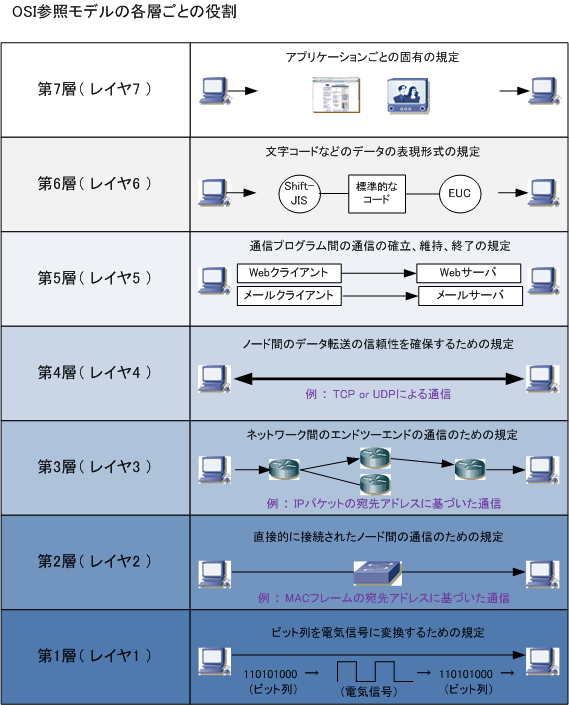
OSI参照モデルでのデータの流れ

ここまでで、OSI参照モデルで定義されているルールの名称がわかりましたね。
では、次は実際にデータがOSI参照モデルではどのように流れていくのかをみていきましょう!
あるデータを通信する時には、必ず箱に入れて運びます。
宅配便と同じイメージです。
宅配便で、配達元から宛先まで荷物を運ぶ時には以下の流れがあります。
1. 運ぶたいものを緩衝材を使ってくるむ
2. ダンボールにいれる。
3. 宛名を貼って
4. 配送表を貼って
5. 宛先へ配送する
そして、受け取った側は逆の順番を行います。
「配送表をはがす」「宛先をはがす」「ダンボールから出す」「緩衝材をとる」で、中身が手に入る。
よく考えると宅配便の作業って結構面倒ですよね?
でも、配送物を緩衝材やダンボールで保護しないと壊れちゃうかもしれない。
宛先を貼らないと、どこへ届けていいかわからない。
そこで、配送物を運ぶためには、いろいろ運びたいもの(データ)以外のものも必要なのです。
実際には、この宅配の流れと同じことがデータ通信でも行われているのです。
つまり、データ通信をする際に、OSI参照モデルの各階層で、運びたいデータ以外のものも付け加えて、宛先に送られます。
この用語のポイントを簡単に!
・データを封詰めしてく感じだよ
・データを封詰めすることをカプセル化と呼んでいるよ
ここまでで、データの流れやデータを運ぶ時にデータ以外の情報も追加されるということが分かったかと思います。
そこで、この章ではOSI参照モデルで、どのようなデータ以外の情報が追加されるのかということを説明していきます。
簡単に言ってしまうと、
OSI参照モデルでは7つの階層があるとお伝えしましたが、上の層から順番に制御データをつけていき、そして、最下層のレイヤ1までいくと電気信号化されて、相手に送られます。
図式化するとこんな感じ
第4層のトランスポート層から、制御データを付加していきます。
ちなみに、トランスポート層で制御データがつくと、「セグメント」と呼ぶ。
第3層のネットワーク層で、制御データがつくと「パケット」、
第2層のデータリンク層で、制御データがつくと「フレーム」
とそれぞれ呼ばれるので覚えておこう。
そして、このようにデータに制御データをくっつけてデータグラムに仕上げることを「カプセル化」という。
データを封詰めしてく感じが、物をカプセルに入れる形と似ているからそう名付けられている。そして、受け取った側はカプセルをはがしていくわけだ。
一連の流れを図式化するとこのようになります。
GIF画像をいれる?
まとめ
1. OSI参照モデルとは
→ 国際標準化機構(ISO)が作ったデータ通信機能におけるモデル
2. OSI参照モデルの7つの階層
→通信データを安全に、簡単に送るために7つの層(レイヤ)に分けたもの。
3. データのカプセル化
→OSI参照モデルでデータが送られる時に制御データをくっつけて作られる、データグラムのこと
OSI 参照モデルとは – 2
今回出てくる用語
・アプリケーション層
・プレゼンテーション層
・セッション層
・トランスポート層
・ネットワーク層
・データリンク層
・物理層
OSI参照モデル : アプリケーション層
この用語のポイントを簡単に!
・OSI参照モデルの中身の分類で
ソフトとの窓口部分に関するルールを定めたものだよ
アプリケーション層は、簡単にいうと「プログラムさんとの窓口になる奴等のあれこれ」が書いてあります。
通信機能は様々なソフトから利用されます。
そのため通信機能にはソフトとの窓口になる部分があります。
この「通信機能のソフトとの窓口部分」に関するルールが定められているのがアプリケーション層です。
例えば、パソコンAがメールサーバに「こんにちは」というメールを送信する場合、メーラーの送信ボタンをクリックすると指定したメールアドレス宛に送信するための処理がコンピュータ上にて開始されますが、この処理がアプリケーション層の部分です。
結果「こんにちは」メッセージと一緒にアプリケーション層で処理された内容が「ヘッダ(通行手形みたいなもの)」として付加されて下位の階層(プレゼンテーション層)にデータが渡されます。
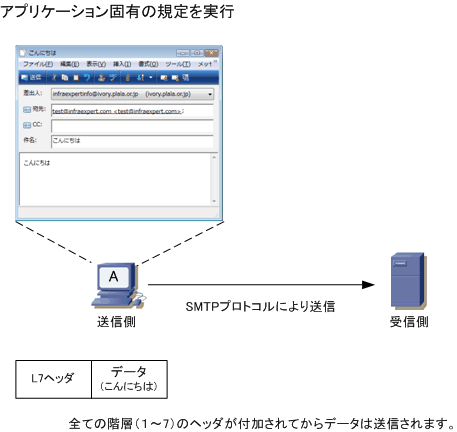
OSI参照モデル : プレゼンテーション層
この用語のポイントを簡単に!
・OSI参照モデルの中身の分類で
コンピュータ側とネットワーク側のデータ形式の変換に関するルールを定めたものだよ
プレゼンテーション層では、データ形式の変換に関するルールが定められています。

わかりやすくご説明するために、交換日記を例にご説明します。

交換日記ですか?

はい!
例えば、私となるほどくんが交換日記をするとします。

なるはやちゃんとですか?どうしようかな、何を書こうかな。

ただし、私はフランス語しか話せません。
そして、なるほどくんは日本語しか話せないとします。

え?!

このままでは2人で交換日記はできませんよね?

そうですね。

そこで、交換日記は英語でやることにしました。
もちろん、私もなるほどくんも頑張って英語で書きました。

た、大変そう。

私は「頭の中」でフランス語で文章を作成し、内容を英語で書き出します。

私は、日本語で文章を考えて、内容を英語で書き出すんですね。

そうです!
これなら、2人で交換日記ができますよね?

そうですね!私となるはやちゃんで英語の勉強もできて一石二鳥!

はい!ということで 、この話における
「頭の中」が「コンピュータ」です。
「日記」が「ネットワーク」に相当します。
「母国語」が「コンピュータが分かるデータ形式」です。
「英語」が「ネットワークで共通のデータ形式」です。

なるほど!

そして「母国語←→英語」の変換に関するルールが定められているのが、プレゼンテーション層なのです。
この層により送信側と受信側のコンピュータで使用している表現形式は異なっていても送信側のコンピュータで「コンピュータ固有の表現形式」から「標準的な表現形式」に変換して送信して、受信側で「コンピュータ固有の表現形式」に変換し直すことで、例えば、文字化けなしに送受信できます。
例えば「文字コード」の表現形式を考えてみます。Windows 7 で日本語の文字コードとして「Shift JIS」を使用しているとします。
一方、UNIXサーバでは文字コードとして「 EUC 」を使用しているとします。
この2つのPCが、プログラム間でデータの表現形式を何も変換しないと文字化けが発生してしまいますが送信側コンピュータで、「標準的な形式(文字コード)」に変換してから送信すれば問題は発生しません。
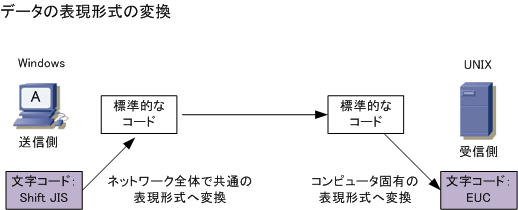
OSI参照モデル : セッション層
この用語のポイントを簡単に!
・OSI参照モデルの中身の分類で
通信の開始から終了までに関するルールを定めたものだよ
セッション層では、通信の開始から終了までに関するルールが定められています。
例えば1つのコンピュータ上でWebブラウザとメーラーを起動させて通信しているとします。Webブラウザで送受信しているデータをメーラーで送受信しないように、各アプリケーション同士の論理的な経路(セッション)を制御しています。セッションが確立するとデータ転送が可能な状態になります。
セッション層の説明では「論理的な通信経路を確立する」といった表現がよく使われます。簡単に言うと、「こっちに注目〜!」と同じ意味です。
「今から私と会話しましょう!注目〜!」が「経路の確立」です。
「もう疲れたので今日は終わりです〜」が「経路の解放」(終了)です。
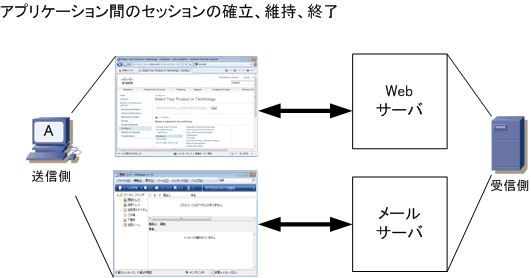
OSI参照モデル : トランスポート層
この用語のポイントを簡単に!
・OSI参照モデルの中身の分類で
目的の機器への「正しい」信号の受け渡しに関するルールを定めたものだよ
トランスポート層では、やり取りの正確さに関するルールが定められています。
難しい表現を使うと「信頼性の確保」というものです。
例えば、相手に「好きです!」と送ったつもりなので、「嫌いです!」と送られたら大変ですよね?
大事な内容であれば正確に伝わらないと困ります。
そこで、この「通信の信頼性」に関するあれやこれやが取り決められているのが、トランスポート層です。
例えば「TCP」や「UDP」と呼ばれている通信プロトコル(通信するときに使うお約束事)はトランスポート層に該当します。
トランスポート層では、ノード(通信機器)間のデータ伝送における信頼性の提供とアプリケーション間でセッションを開始する上で必要なポート番号の割り当てについて規定しています。
データ伝送における信頼性を確保するために、ノード(通信機器)間においてはコネクションの確立、エラー制御、フロー制御、順序制御などを行っています。
アプリケーション同士の論理的な経路をセッションと言い、ノード(通信機器)間における論理的な経路はコネクションと言います。
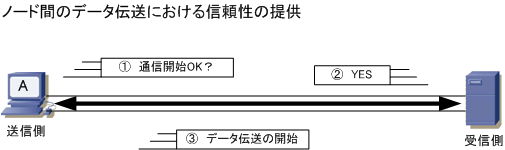
※セッションとコネクションを同じ意味で使用している解説もありますが、セッションとコネクションの厳密な違いは以下です。(参考程度に見ておきましょう。)
| セッションとコネクションの違い | 説明 |
| セッション | セッションは、通信の開始から終了までを管理する1つの単位のことです。 例えば端末の間でセッションが確立すると、通信で使用するアプリケーションが データ転送可能な状態になります。OSI 7階層の第5層「セッション層」の機能です。 |
| コネクション | コネクションは、セッションでデータ転送を行うための論理的な回線のことです。 一般的に、OSI 7階層の第4層「トランスポート層」のTCPコネクションを指します。 |
OSI参照モデル : ネットワーク層
この用語のポイントを簡単に!
・OSI参照モデルの中身の分類で
通信相手とのやり取りに関するルールを定めたものだよ
ネットワーク層では、ネットワーク層では送信元と送信先のやり取りに関するルールが定められています。
例えば
ネットワーク層では、送信元のコンピュータからのデータをスイッチ、ルータ等の機器を経由して、宛先のコンピュータへ届けるためにソフトウェアアドレス(具体例:IPアドレス)を通信機器に割り当て、ルータはこのソフトウェアアドレスに基づき、宛先のコンピュータまでの最適なパスを選択してデータを送信します。
この「目的の機器とのやり取り」に関するあれやこれやが取り決められているのが、ネットワーク層です。
※宛先のコンピュータまでパケットを送信する時に、最適な経路を選択してパケット送信することをルーティングといいます。
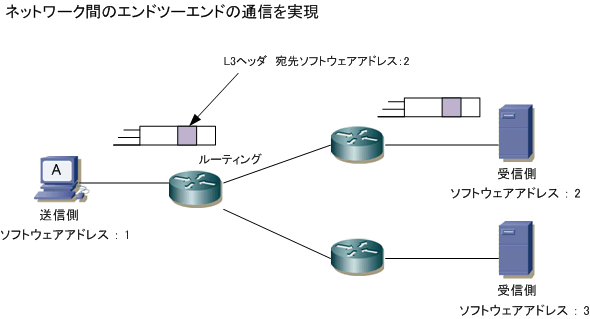
OSI参照モデル : データリンク層
この用語のポイントを簡単に!
・OSI参照モデルの中身の分類で
直接つながっている機器とのやり取りに関するルールを定めたものだよ
データリンク層では、直接つながった機器とのやり取りに関するルールが定められています。
直接つながった機器というのは、
例えば、「パソコンとLANケーブルでつながったルータ」や「パソコンと無線LANアクセスポイント」のようなものです。
データリンク層ではLANで各ノード(通信機器)にハードウェアアドレス( 例 : MACアドレス )を割り当て、その情報をもとに通信を行います。
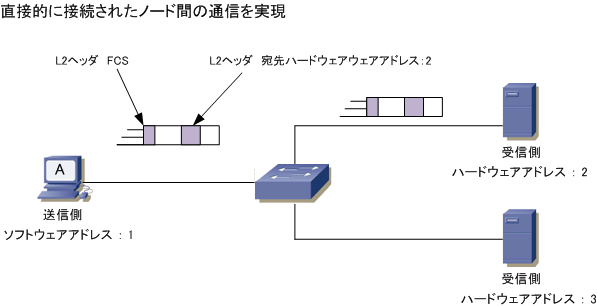
OSI参照モデル : 物理層
この用語のポイントを簡単に!
・OSI参照モデルの中身の分類で
ケーブルやコネクタ、電気信号等の物理的なものに関するルールを定めたものだよ
物理層ではケーブルやコネクタ、実際にデータを変換した電気信号など、その名の通り物理的な物のルールが定められています。
厳密にいうと、ネットワークの物理的な接続や伝送方式を規定しています。
ノード(通信機器)からのデータを送信する場合はコンピュータ内部で使用している「0」と「1」のビット列を電気信号に変換しネットワークへ伝送を行います。
また、ノード(通信機器)がネットワークから信号を電気受信する場合は、受信した信号をノードが理解できるように信号を「0」と「1」のビット列に変換して、コンピュータ内部に情報を取り込みます。物理層はPHYとも言います。
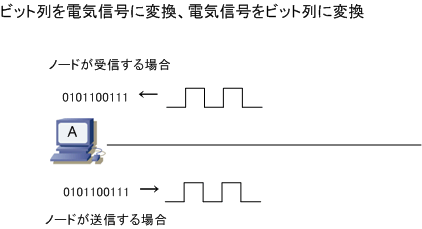
まとめ
・アプリケーション層とは
→通信機能のソフトとの窓口部分に関するルールを定めたもの
・プレゼンテーション層とは
→データ形式の変換に関するルールを定めたもの
・セッション層とは
→通信の開始から終了までに関するルールを定めたもの
・トランスポート層とは
→目的の機器への「正しい」信号の受け渡しに関するルールを定めたもの
・ネットワーク層とは
→通信相手とのやり取りに関するルールを定めたもの
・データリンク層とは
→直接つながっている機器とのやり取りに関するルールを定めたもの
・物理層とは
→ケーブルやコネクタ、電気信号等の物理的なものに関するルールを定めたもの
ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストの違い
今回出てくる用語
・ユニキャスト
・マルチキャスト
・ブロードキャスト
ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストとは

ここまでで、OSI参照モデルの説明をしてきましたが、ここで通信方式の種類に関してご説明していきます。

お願いします!
コンピュータネットワークで通信を行う場合、通信相手の数によって以下の3種類の通信に分類できます。
| 通信方式 | 説明 |
| ユニキャスト | ユニキャストとは、単一のアドレスを指定して、1対1で行われるデータ通信のことです。 |
| マルチキャスト | マルチキャストとは、特定のアドレスを指定して、1対複数で行われるデータ通信のことです。 |
| ブロードキャスト | ブロードキャストとは、同じネットワーク内の全宛先を指定し、1対不特定多数で行われるデータ通信。 |
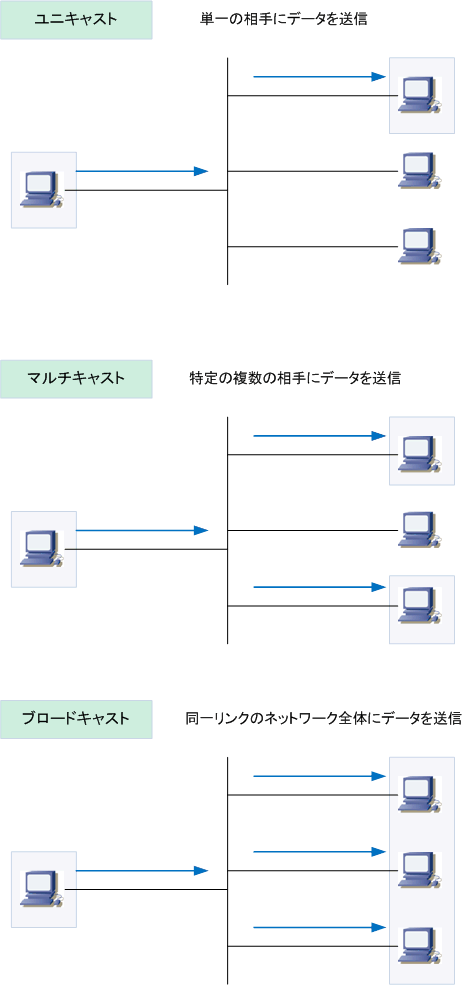
文字で書くとこんなイメージです。
・ユニキャスト:1対1
・マルチキャスト:1対多
・ブロードキャスト:1対多(全員)
ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストの用途
この用語のポイントを簡単に!
・ユニキャスト通信は、WEBサイトの閲覧や電子メールの送受信で使われるよ。
・マルチキャスト通信は、動画配信で使われるよ。
・ブロードキャスト通信は、ユニキャスト通信の最初に使われるよ。
・ユニキャスト通信の用途
通信相手先を指定して1対1で通信するもっとも標準的な通信です。
例えば今、あなたのPCは私のWebサーバとユニキャスト通信をすることでこのWebサイトを閲覧しています。
このように、Webサイトの閲覧、電子メールの送受信など、色々な用途で最も使用されている通信方式です。
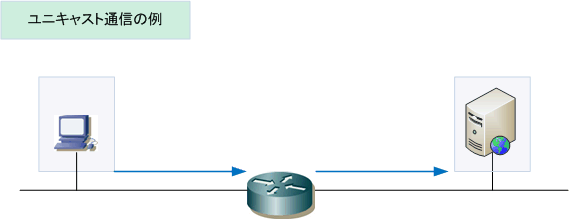
・マルチキャスト通信の用途
マルチキャストアドレスという特殊なアドレス(224.0.0.0~239.255.255.255)を使用して、特定のグループに所属する全てのPCにデータを送る通信方式です。
このマルチキャスト通信はネットワーク上の動画配信などでよく使用されます。
マルチキャストなら、送信元のコンピュータが送信する1つのパケットをマルチキャスト対応ルータなどで複製し、同時に宛先の数だけそのパケットを送信します。
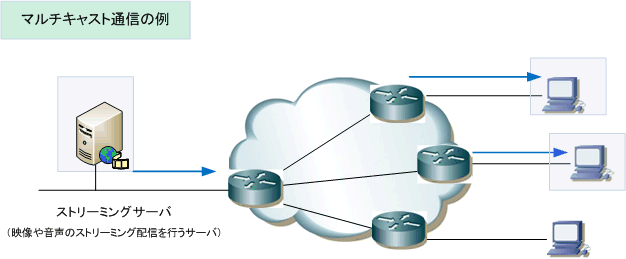
ユニキャストであると通信したい宛先に1つずつパケットを送出する必要があり、動画や音楽などを容量の大きいデータを多数の宛先に送信するためには非常に負荷がかかるので、マルチキャストは効率的です。
・ブロードキャスト通信の用途
ブロードキャストアドレスというアドレスを使用して同一LANの全てのノードにデータを送る通信方式です。ブロードキャストの用途として、IPアドレスからMACアドレスの情報を求めるARPで利用したり、IPアドレス取得のためDHCPで利用したりルーティング情報のアップデートで使用します。
ブロードキャスト通信は、ユニキャスト通信を実現する上で最初に行われる大切な通信であるとも言えます。
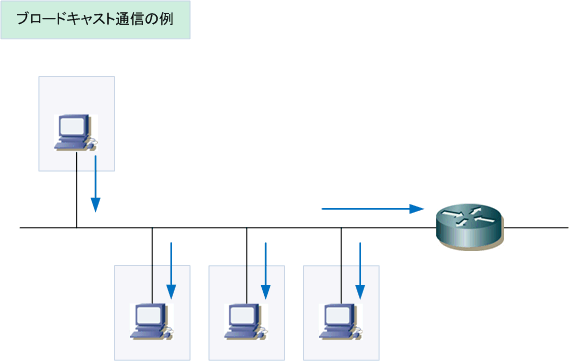
まとめ
・ユニキャストとは
→1対1で行われるデータ通信のこと。Webサイトの閲覧、電子メールの送受信などでよく利用される。
・マルチキャストとは
→1対複数で行われるデータ通信のこと。動画配信などでよく利用される。
・ブロードキャストとは
→同一のネットワーク全体の機器とのデータ通信のこと。ユニキャスト通信の最初に使われる通信。
2進数と10進数との変換
今回出てくる用語
・2進数

では、次はコンピュータの内部で利用される数値についてご説明します。

コンピューターが使う数字ですか?

そうです!コンピューターはあらゆるデータをこの数値で表現しています。

そうなのですね!?

はい!具体的にどんな数値を使っているのか教えていきますね!

お願いします!
コンピュータで使用される2進数
この用語のポイントを簡単に!
・コンピュータが理解でするための数値だよ
・0と1だけで表現するよ
人が日常使用している数値は10進数ですが、コンピュータの世界では、2進数が標準です。
しかし、「0」と「1」だけの2進数では人が分かりにくいため、人間が見えるところでは
コンピュータは2進数を10進数や16進数に変換して表現しています。
ここではその変換方法を学びましょう。
2進数では、「0」と「1」の2種類の数字を用いて全ての数を表現され、それぞれの桁の数字が「2」になると桁上がりするのが「2進数(ニシンスウ)」です。
位があがれば、その新しい桁は 「 1 」 となり、それ以下の桁は全て 「 0 」 となります。それでは、2進数の数の増え方を見てみましょう。
![]()
ところで、2進数を表現する時は一般的に8桁単位で表現するため、8桁未満の場合は頭に0をつけます。
つまり、上の2進数の値は順番に
00000000 → 00000001 → 00000010 → 00000011 → 00000100 →00000101 → 00000110 → 00000111 → 00001000 と表します。
以下は2進数と10進数の対応表です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ・・・ |
| 0 | 1 | 10 | 11 | 100 | 101 | 110 | 111 | 1000 | 1001 | 1010 | ・・・ |
2進数から10進数への変換方法
この用語のポイントを簡単に!
・2進数→10進数の計算では、2の累乗が何個あるかを考えると便利だよ
・2の累乗をある程度暗記しておくと便利だよ
10進数と2進数の対応表は下記の通りです。
10進数:2進数
0:0
1:1
2:10
3:11
4:100
5:101
6:110
7:111
8:1000
9:1001
10:1010
これを暗記しておくのは結構大変ですので、良い計算方法をお伝えいたします。
上の10進数と2進数の対応表は位は右から順に
1(2の0乗)の位
2(2の1乗)の位
4(2の2乗)の位
8(2の3乗)の位
16(2の4乗)の位
32(2の5乗)の位
64(2の6乗)の位
128(2の7乗)の位
256(2の8乗)の位
512(2の9乗)の位
1024(2の10乗)の位
2048(2の11乗)の位
・
・
と並びます。
つまり、それぞれの桁は2の累乗が何個あるかを示しています。
例えば、2進数で
100101
という数字があったとしましょう。
これを10進数に直す場合、以下の手順で計算をしていきます。
- 「1」が何の位にあるのかを確認
- その位に応じた乗数を足し合わせる
そのため、今回の場合は
1.「1」が何の位にあるのかを確認
→ 1つ目、3つ目、6つ目に「1」の表示がありますね。
2. その位に応じた乗数を足し合わせる
→ (2の0乗) + (2の2乗)+(2の5乗)
つまり、
(2の0乗)= 1
(2の2乗)= 4
(2の5乗)= 32
となり、この数字を全て足し合わせると
1 + 4 + 32 = 37
と答えが出る。
つまり、100101(2進数) = 37 (10進数)
ということになる。
10進数から2進数への変換方法
この用語のポイントを簡単に!
・10進数の数値を割り算して、余りの数を下から数えると便利だよ
10進数の数値を「 0 」になるまで「 2 」で割り算していき、その結果の「余りの数 」を並べることで10進数の値を2進数の値へ変換することができます。
それでは、具体的に変換して見て行きましょう。
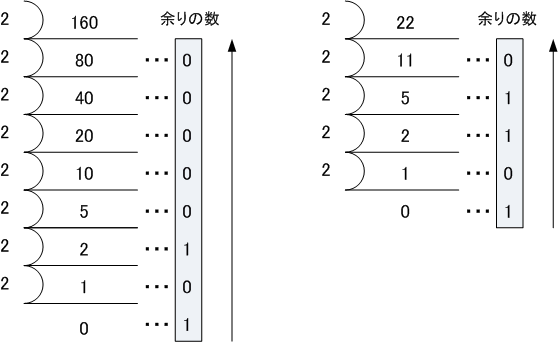
例えば、10進数の「160」を2で割り算していくと上図の結果となります。後は、余りの数を下から順番に並べれば 「 10100000 」 の値が算出されます。
次に、「22」を2で割り算していき余りの数を下から順に並べれば 「 10110 」 の値が算出されます。
ネットワークにおいては、2進数を一般的に8桁で表示することから、8桁になるよう上位に「 0 」を追加して「 00010110 」とします。当然「 10110 」と同じ値です。

2進数⇄10進数の計算方法をご紹介しましたが、一体どんな場面で2進数は使われていると思いますか?ヒントは「0」「1」の2種類でやり取りができることです。

んー、何でしょうか?

例えば、みなさんスマホをタッチしてアプリを起動しますよね?

はい!

そのときにアプリをタッチしたという信号は「0」と「1」で表現されています。例えば、タッチしたら「1」、離したら「0」のように信号を送っています。

あ!なるほど!

このように目には見えないけども、エンジニアにとっては大切な仕組みなのでぜひ覚えておきましょうね!
まとめ
・2進数とは
→コンピュータが理解できる数値形式で、「0」と「1」で表現される。
ネットワークをはじめから – 2進数と16進数との変換
今回出てくる用語
・16進数
16進数について

ここまでで、コンピュータが2進数を使って数値の理解をしているということは分かったと思います。
それでは、次は16進数というものも説明していきます。

え!?16進数ですか?

はい。16進数はコンピュータの世界ではよく使われる数値で、
例えば「色コード」や「IPアドレス」も16進数を使ってコンピュータが理解できるようにしています。

なるほど!

それでは、16進数も重要なのでぜひ覚えちゃいましょう!
10進数の基数は「10」、2進数の基数は「2」、そして16進数の基数は「16」であることから、16進数では16種類の数字が必要であることが分かります。
記号としての数字は 「 0 ~ 9 」 の10種類しかないので、16進数ではアルファベットの 「 A~F 」を数字として使用します。
10進数は 「 9 」 の次に位が上がるか16進数では 「 F 」 の次に位があがります。
なお、10進数の数値と区別するために、16進数では数値の先頭に「 0x 」をつけます。以下の対応表通り、例えば10進数の「 8 」は16進数では「 0x8 」となります。
| 10進数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16進数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 |
2進数から16進数への変換方法
2進数の数値を16進数の数値に変換するためには、3つのステップを踏む必要があります。
16進数の1桁を2進数では4桁で表すため、以下の順番で計算をしていきます。
1. 2進数の数値を4桁の数値に分離します。
2. 分離した数から10進数の値を求めます。
3. その10進数の値を16進数に変換します。
例えば、「10110110」という2進数を16真数に直す場合
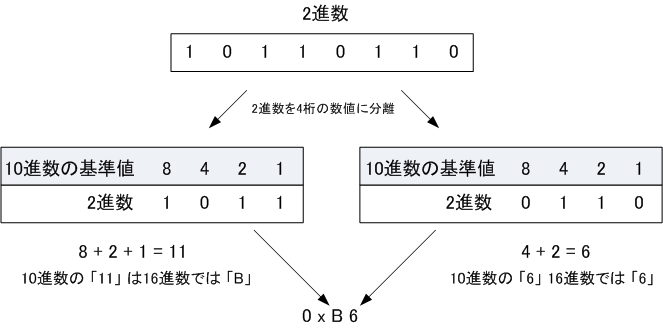
以上のことから、2進数の数値「 10110110 」は16進数の数値に変換すると「 0xB6 」であると分かります。
16進数から2進数への変換方法
次は、16進数の数値を2進数の数値に変換する方法をご説明します。
1. 16進数の1桁を2進数の4桁に変換します。
2. その4桁の数値を並べる
上図と同様で、16進数の数値からいきなり2進数の数値を求められない場合、16進数の数値を一度10進数の数値に変換し、10進数の数値から2進数を求めるようにします。
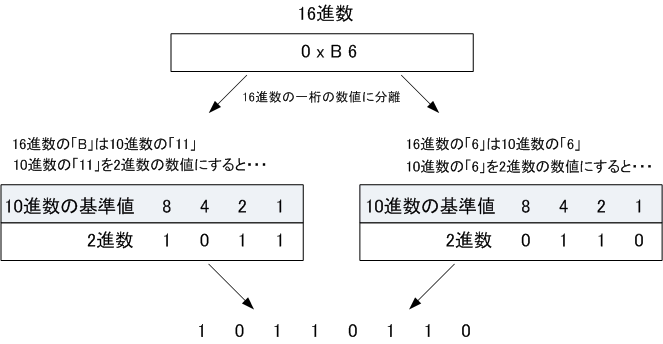
以上のことから、16進数の数値「 0xB6 」は2進数の数値に変換すると「 10110110 」であると分かります。
10進数から16進数への変換方法
次は、10進数の数値を16進数の数値に変換する方法をご説明します。
1. 10進数の数値を2進数の数値に変換する
2. 2進数の数値を16進数の数値に変換する
つまり、10進数から直接16進数に変換するのではなく「 2進数への変換 」を経由します。ただし数値が小さい場合は直接変換した方が早いでしょう。
ここでは10進数の「160」の数値は、16進数では「0xA0」であると導きだしています。考え方は今までと同じです。
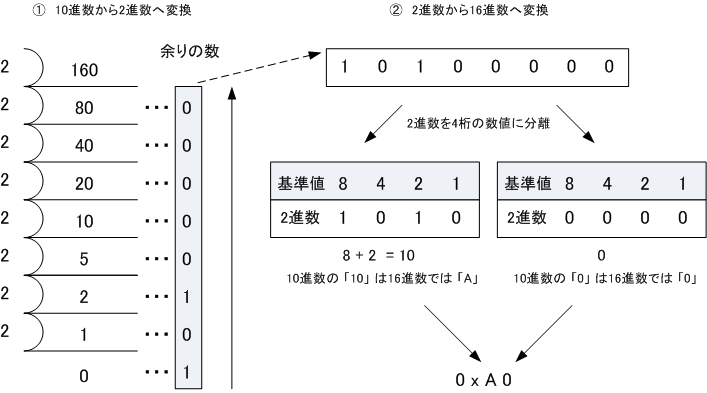
16進数から10進数への変換方法
16進数から10進数に変換する場合も、「2進数への変換」を経由することで数値を算出します。
ここでは、16進数の「0xB6」の数値は、10進数では「182」であると導きだしています。考え方は今までと同じです。
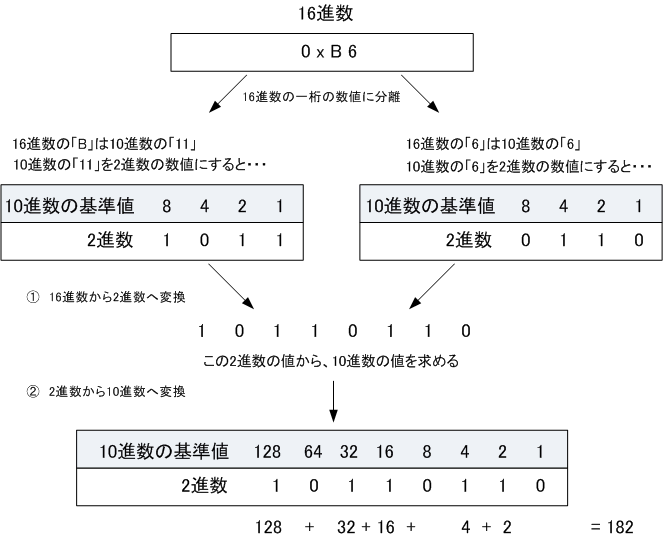
まとめ
・16進数とは
→数字とアルファベットを使って16個の記号で表した数値。コンピュータの色コードやIPアドレスなどで利用されている。
※最新の情報の取得・更新に努めておりますが、掲載内容については、その正確性、完全性、有用性、最新性等についていかなる保証もするものではありません。